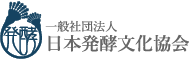ブログ
続・(大学生による)第6回「発酵定例会」プチレポート
こんにちは。発酵マイスター・発酵ライターの大学生、佐藤友理(ゆり)です。
私の発酵コラムでは前回から、第6回「発酵定例会」での、
4人の先生による特別講演のプチレポートをさせていただいております。
前回の発酵コラム→「第6回発酵定例会」に初参加!
今回は、後半2つの特別講演を振り返ってみます。
(1)東京農業大学 教授 柏木豊 先生
(2)NPO法人 桶仕込み保存会 セーラ・マリ・カミングスさん
の講義に続いて、
(3)第一酵母株式会社 多田一政さんの講義では、
単一培養酵母と複合培養酵母の違いや、体への影響について学びました。
![DSC00406[1]](../../../old/uploads/2015/09/DSC004061-150x150.jpg)
天然酵母フルーツ飲料「コーボン」に使われている伊豆酵母は、
気候・海流・地形・植生などの条件がばっちりそろった、奇跡の野生酵母だそうです。
100℃でも死滅しない酵母だなんて、なんとワイルドでたくましいのでしょうか。
![DSC00407[1]](../../../old/uploads/2015/09/DSC004071-150x150.jpg)
試飲でいただいた「コーボン」は、さっぱりとした甘味がさわやかで、とてもおいしかったです。
![DSC00408[1]](../../../old/uploads/2015/09/DSC004081-150x150.jpg)
続いて、
(4)一般社団法人 大人のダイエット研究所 所長 岸村康代さんの講義では、
発酵食品と腸内環境について学びました。
気になったキーワードが2つありました!
「酒粕のレジスタントプロテイン」
「セカンドミール効果」
に注目です!!
まず
「酒粕のレジスタントプロテイン」です。
「レジスタント」というのは、「消化しにくい」という意味です。
酒の原料の米が発酵することによって、人の体内で消化しにくいたんぱく質ができるのです。
この成分は、食物繊維のような働きがあり、お通じもよくなります。
これから秋冬にかけて寒くなってくると、粕汁やお鍋の季節ですので、酒粕の出番ですね。
そして私が酒粕を語るにあたり、忘れてはならないのが、「粕漬け」です。
粕漬けといえば、「奈良漬」!
私は大学生になって、奈良に住むようになりましたが、
観光客の方向けに奈良漬屋さんがたくさん近所にあるものの、
私自身、買い求めることは多くありません。奈良での生活も卒業までの残り1年半。
発酵マイスターとして、奈良漬の研究もやってみたいです。
2つ目の注目キーワードは
「セカンドミール効果」です。
![DSC00403[1]](../../../old/uploads/2015/09/DSC004031-150x150.jpg)
ざっくり言うと、「朝食に何を食べるかが大切」ということだと思います。
![DSC00404[1]](../../../old/uploads/2015/09/DSC004041-150x150.jpg)
朝に、食物繊維が多いものを食べると、昼や夜の食事で血糖値の上昇がゆるやかになります。
![DSC00405[1]](../../../old/uploads/2015/09/DSC004051-150x150.jpg)
つまり、「太りにくい体を維持できる」といえるのだそうです。
白砂糖たっぷりの菓子パンやジュースよりも、
麦ごはんや大豆製品のほうが「セカンドミール効果」が期待できます。
私は大学で、「栄養教育論」などの講義・実習などを通して、
「栄養カウンセリング」の手法などを学びました。
何がきっかけで、食生活を健康的なものへと自ら改善していくのかには、個人差があります。
たとえば私なら、「セカンドミール効果」のように、論文に出てきそうな用語を耳にすると、
すぐに飛びついて、次の日の朝食から麦ごはんを炊くかもしれません。ミーハーなタイプです^ ^
「言葉の魔法」ってありますよね…
発酵食品のすばらしさを伝えるときも、言葉一つでいくらでも魅力的になります。
現代のライフスタイルにも十分調和していくものとして
素敵な発酵文化を発信できるのではないかと思いました。
今回も最後までお読みくださり、ありがとうございました!